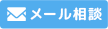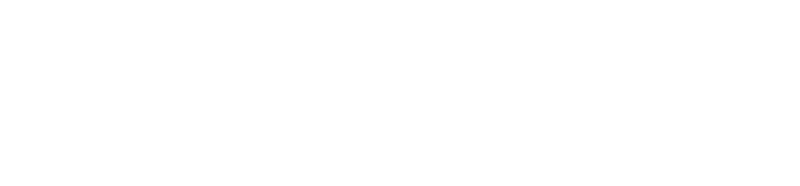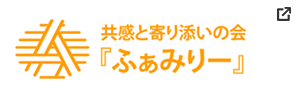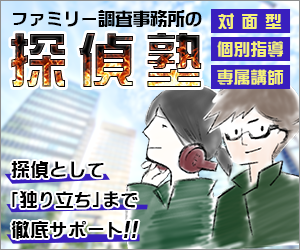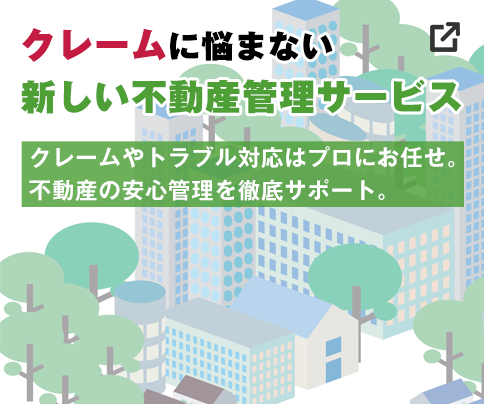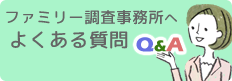知的財産権は、企業の価値を支える資産です。
特に商標権は、自社ブランドの顔として消費者の信頼を獲得し、競合他社との差別化を図るうえで欠かせない権利です。
しかし、模倣品の流通やロゴの無断使用など、商標権侵害の脅威は年々増加しています。
この記事では、商標権侵害の基礎から商標権保護まで、解説しています。
記事を読むことで、ブランド価値の構築と事業の安定性を確保できるでしょう。
目次
知的財産権における商標権侵害とは?
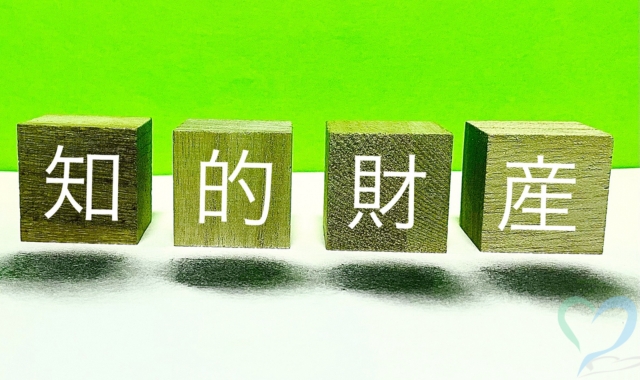
知的財産権における商標権侵害とは、他者が登録した商標を無断で使用する行為のことです。
商標権が侵害されると、消費者が本物と偽物を区別できなくなるため、企業の評判や売上に大きな損害が出る可能性があります。
企業が安心してビジネスを展開するためには、商標権と商標権の侵害を正しく理解することが重要です。
この章では、商標権の基本と保護対象、商標権侵害の具体例をご紹介します。
商標権の基本と保護対象

商標権とは、特定の商品やサービスに使用する標識を独占的に使用できる権利のことです。
(※1)簡単に言えば、自社のロゴや商品名を他社が勝手に使えないようにする法的な守りです。
商標権には、以下3つの重要な目的があります。
1.企業の信用やブランド価値を守る
2.産業全体の発展に貢献する
3.消費者が商品の出どころを正しく識別できるよう保護する
(※2)
商標法で保護される対象は、以下のとおりです。
・文字
・図形
・色彩
・記号
・動き
・位置
・ホログラム
・立体的形状
・色彩のみ (※3・4)
商標権侵害の具体例

商標権侵害の具体例として、モンシュシュ事件やバーキンバッグ事件があげられます。
モンシュシュ事件とは、ゴンチャロフ製菓と株式会社モンシュシュの間で起きた商標権侵害訴訟のことです。
この事件では、ゴンチャロフ製菓が1981年に登録していた「モンシュシュ」の商標を、株式会社モンシュシュが、店舗の看板・商品の包装・広告などに使用していたことが商標権侵害にあたるとして争われました。
その結果、2011年に大阪地方裁判所において商標権侵害と認められ、株式会社モンシュシュに、約3,500万円の損害賠償金の支払いが命じられました。
株式会社モンシュシュは控訴しますが、2013年に大阪高等裁判所においても商標権侵害が認められ、賠償額が約5,100万円に増額されています。
この判決を受け、株式会社モンシュシュは2012年10月1日に社名を「株式会社モンシェール」に変更するというダメージを受けます。
バーキンバッグ事件は、エルメス・アンテルナショナルがバーキンバッグの立体商標権にもとづき、株式会社DHS corpを商標権侵害で訴えた事件です。
訴訟の結果、2014年5月21日に東京地方裁判所が商標権侵害を認め、株式会社DHS corpに対し235万8,400円の損害賠償金の支払いを命じました。
この判決は、高級ブランド品の形状も立体商標として保護されることを示す重要な先例となっています。
商標権侵害が認定されれば、高額な損害賠償金の支払いや社名変更などを余儀なくされます。
企業の信用を損なわないためにも、商標権侵害には注意が必要です。
知的財産権侵害における商標権侵害の判断基準

知的財産権における商標権侵害の判断基準には、商標・商品・サービスの類似性があげられます。
類似の判断基準「外観・称呼・観念」の3要素
商標権侵害の判断において、類似性は「外観・称呼・観念」の3要素から総合的に評価されます。
これらの要素が似ていると、消費者が「どの企業の商品なのか」間違えてしまう可能性があります。
商標権の類似性を判断する3つの要素の定義と判断のポイントを、以下の表にまとめました。
| 要素 | 定義 | 判断のポイント |
| 外観 |
|
見た目の印象が消費者に混同を生じさせるか |
| 称呼 |
|
発音した際の聴覚的印象が類似しているか |
| 観念 | 商標から連想される意味や概念 | 商標から想起される意味や概念が同一か類似しているか |
上記の要素のうち、どれか一つでも強い類似性があれば、商標権侵害と判断される可能性があるため注意が必要です。
商標権侵害を回避するためには、新しい商標を使用する前に、既存の商標との類似性を3つの要素から検討する必要があります。
商品・サービスの類似性はどう判断される?
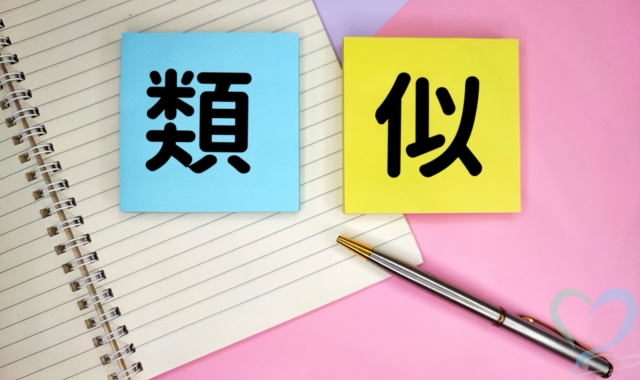
商標権侵害における商品・サービスの類似性は、以下4つの視点から判断されます。
| 判断基準 | 説明 | 具体例 |
| 生産者の共通性 | 同じ会社やメーカーが両方の商品を製造するのが一般的かどうか | チョコレートとクッキーは同じお菓子メーカーが製造するため類似と判断されやすい |
| 販売場所の共通性 | 同じ店舗や売り場で販売されることが多いかどうか | シャンプーとリンスはスーパーやドラッグストアの同じ棚に並ぶため類似と判断されやすい |
| 用途の共通性 | 使用目的や機能が関連しているかどうか | スマートフォンとスマートフォンケースは使用目的が関連しているため類似と判断されやすい |
| 需要者の共通性 | 同じ消費者層が購入することが多いかどうか | おむつとベビーフードは同じ消費者が購入するため類似と判断されやすい |
なお、特許庁では商品やサービスを「類似群コード」という5文字の番号でグループ分けしています。
同じコードが付いている商品やサービスは、類似性があると考えられます。(※)
商標権を侵害しないためには、新しい商品名やロゴを使用する前に調査を行ったり、弁護士や弁理士などの専門家に判断をあおいだりするのが得策です。
商標権を含む知的財産権が侵害されたときの対応策4ステップ
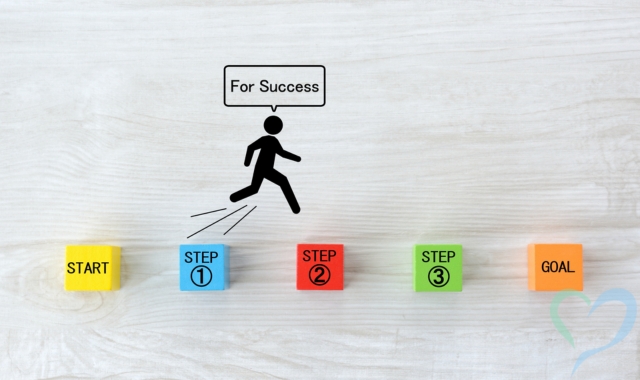
商標権を含む知的財産権が侵害されたときの対応策には、以下の4ステップがあります。
1.侵害発見時の初期対応と証拠保全
2.警告書の送付と和解交渉
3.法的措置の検討と実行
4.損害賠償請求の実施
対応策を把握することで、商標権を侵害された場合でもスムーズに対応できるでしょう。
ステップ1:侵害発見時の初期対応と証拠保全

知的財産権の侵害を発見したら、証拠を確保することが重要です。
なぜなら、法的措置を実行する場合、証拠は侵害の事実を証明するものになるからです。
例えば、侵害商品の購入や関連広告の収集、Webサイトのスクリーンショットなどが有効な証拠になります。
知的財産権の侵害を発見したら、すぐに証拠を集め、日付や入手経路を記録しておきましょう。
また、証拠収集と並行して、侵害の範囲や程度を正確に把握することも大切です。
自社の権利がどのように侵害されているのか、市場にどの程度の影響があるのかを調査します。
次のステップをスムーズに進めるために、侵害者の情報も可能な限り収集しておきましょう。
この段階で、弁護士や弁理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
専門家であれば、侵害の事実確認や証拠の評価、今後の対応策について適切なアドバイスを提供してくれます。
ステップ2:警告書の送付と和解交渉

証拠を集めた後は、侵害者に警告書を送付します。
正式な警告により侵害行為が停止し、訴訟など費用のかかる手段を避けられるケースが大半です。
警告書には侵害の具体的内容・停止を求める行為・対応期限を明記しましょう。
侵害者から回答があれば、和解交渉に移ります。
和解交渉では、侵害行為の即時停止や損害の賠償、謝罪文の掲載などの条件を話し合います。
ステップ3:法的措置の検討と実行

警告や交渉で解決しない場合は、法的措置を検討します。
侵害行為を確実に止め、正当な賠償を得るためには、裁判所の力を借りる必要があるからです。
民事訴訟を起こして差止請求をすれば、相手に侵害商品の製造・販売をやめさせたり、使用している設備を撤去させたりできます。
また、差止請求には仮処分という方法もあり、本格的な裁判を待たずに、裁判所に「侵害行為をやめさせてください」と申し立てることも可能です。
悪質な侵害の場合は、刑事告訴という選択肢もあります。
商標権侵害は犯罪であり、最大10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)の罰則があります。(※)
ただし、刑事告訴は警察や検察の判断に委ねられるため、確実性はありません。
そのため、法的措置を取る場合は、民事訴訟で差止請求や損害賠償請求をするのが有効です。
ステップ4:損害賠償請求の実施

最後のステップでは、侵害により受けた損害額を請求します。
知的財産権が侵害された場合、売上が減少したり企業の評判が低下したりするため、それを回復させる資金が必要です。
商標権侵害の場合、侵害した人が得た利益や、本来支払われるはずであった使用料を請求できます。(※1)
損害賠償請求の方法には、不法行為の考えにもとづくものと、商標法などの特別な法律によるものがあります。
特に商標法では、侵害した人が得た利益を権利者の損害と考えて良い特別なルールがあるため、損害額の推定が容易に可能です。(※2)
また、お金の賠償以外にも、侵害により傷ついた企業の評判を回復するために、新聞やWebサイトへの謝罪文の掲載も求められます。
これにより、市場での自社ブランドの価値を守れます。
※参考:商標法第三十八条|e-GOV法令検索(※1・2)
知的財産権侵害と商標権侵害における経営者の法的責任

知的財産権侵害と商標権侵害における経営者の法的責任は、以下の2つです。
- 取締役の第三者に対する責任
- 善管注意義務と商標権侵害
法的責任を把握することで、法的リスクの回避と企業の持続的な経営が可能になるでしょう。
取締役の第三者に対する責任(会社法四百二十九条一項)

取締役は会社だけではなく、第三者に対しても法的責任を負う場合があります。
なぜなら、会社法第四百二十九条一項により、以下のように定められているからです。
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
例えば、他社の商標権を侵害する商品の販売を把握しているにもかかわらず放置した場合、取締役個人が損害賠償責任を負う可能性があります。
そのため、経営者は、自社の事業活動が他社の知的財産権を侵害していないか注意を払うことが重要です。
会社の運営に関与している人が登記上の取締役ではない場合でも、事実上の取締役として会社法第四百二十九条一項が適用され、責任を問われるケースがあります。
友人や親族に頼まれて取締役の名前を貸した場合も、同様に責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
善管注意義務と商標権侵害

取締役は会社に対して、善管注意義務と忠実義務の責任を持っています。(※1・2)
これに違反して商標権侵害を行った場合、第三者への責任が発生します。
なぜなら、会社が第三者の商標権を侵害しないよう配慮するのも取締役の任務だからです。
例えば、新商品の作成時には、他社の商標に似たブランド名やロゴなどを使用していないか確認する必要があります。
もし、他社の商標権を侵害しているか否か判断できない場合は、専門家に相談するのが得策です。
万が一、商標権を侵害した場合は、商品の販売を止められたり損害賠償金を支払ったりしなければいけません。
悪質な場合は、刑事罰として最大10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されるケースもあります。(※3)
実際、2021年9月28日、大阪地方裁判所において、他社の特許権を侵害した取締役が個人的に損害賠償責任を負うという判決が出ました。
これは、裁判所から侵害の可能性を指摘されたのにもかかわらず、専門家に相談せずに商品の販売を続けた行為が悪質と判断されたためです。
法的責任を回避するためには、経営者として他社の知的財産権を尊重する会社作りや侵害を防ぐための仕組みを構築することが大切です。
※参考:民法第六百四十四条|e-GOV法令検索(※1)
会社法第三百三十条|e-GOV法令検索(※2)
商標法第七十八条|e-GOV法令検索(※3)
知的財産権と商標権を侵害から守る予防策

知的財産権と商標権を侵害から守る予防策は、以下のとおりです。
- 事前調査と専門家への相談
- 商標登録による権利保護
- 社内体制の整備と従業員の教育
予防策を把握することで、長期的なブランド構築や事業の安定性確保が可能になります。
事前調査と専門家への相談

新しい商品名やロゴを使用する前に、調査を行いましょう。
他社の商標権を侵害してしまうと、高額な損害賠償や社名・商品名の変更を強いられるリスクがあるからです。
効果的な事前調査の方法として、特許情報プラットフォームの活用があげられます。
特許情報プラットフォームは、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営している無料の特許情報検索・閲覧サービスです。(※)
特許情報プラットフォームを活用する際は、自社の商標と完全一致するもの以外にも、類似している商標がないか確認しましょう。
類似商標の存在を見落とすと、商標権の侵害で訴えられる恐れがあります。
事前調査を行った後は、弁護士や弁理士などの専門家へ相談するのがおすすめです。
専門家に相談すれば、使用予定の商標が他社の権利を侵害する可能性を、判例や法律にもとづいて評価してもらえます。
また、ライセンス契約やコラボレーション契約など、知的財産権にかかわる契約書の内容を法的観点からチェックしてもらえます。
これにより、不利な条件や将来的なリスクとなる条項を事前に発見でき、将来のトラブルを防止できるでしょう。
専門家への相談費用は、高額な損害賠償と比較すれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。
特に、海外展開を検討している場合は、各国の法制度に精通した専門家からのアドバイスが不可欠です。
最終的には、事前調査と専門家の意見を総合的に検討したうえで、他社の商標権を侵害するリスクが低く、自社のビジネスに適した商標を選択してください。
※参考:J-PlatPat操作マニュアル|独立行政法人工業所有情報・研修館
商標登録による権利保護

自社のブランドやロゴは、早めに商標登録して権利を保護するのがベストです。
なぜなら、商標登録制度は「先願主義」にもとづいているため、同一または類似の商標は先に出願した人に権利が与えられるからです。(※1)
万が一、他社が先に自社と同じブランド名やロゴを商標登録した場合、そのブランド名やロゴを使用できなくなるうえに、商標権の侵害として訴えられる可能性があります。
商標登録により得られる権利は、以下の2つです。
| 権利の種類 | 内容 | 効果 |
| 専用権(※2) | 登録商標を独占的に使用できる権利 | 自社のみが商標を使用可能 |
| 禁止権(※3) | 他者による類似商標の使用を差し止める権利 | 模倣品の販売差し止めや損害賠償請求が可能 |
上記の権利により、自社のブランド価値を守れます。
商標権は一度登録すれば10年間有効で、更新手続きにより半永久的に権利を維持できますが、以下の点に注意が必要です。
- 更新を忘れると権利が消失するため管理システムを整えておく必要がある
- 商標権の効力は登録した商品・サービスの区分内に限られるため事業範囲を考慮する
- 将来の事業展開を見据えて適切な区分で登録する
また、登録のみで3年以上使用していない商標は、不使用取消審判により権利が取り消されます。
不使用取消審判とは、日本国内において継続して3年以上商標が使用されていない場合に、誰でもその商標を取り消せる制度のことです。(※4)
そのため、登録商標は実際のビジネスで継続的に使用する必要があります。
なお、商標登録の手続きは自分でできますが、類似商標の調査や適切な区分の選定など、専門的な知識が必要であるため弁理士や弁護士などに依頼するのがおすすめです。
※参考:商標法第八条・第二十五条・第三十七条・第五十条|e-GOV法令検索(※1・2・3・4)
社内体制の整備と従業員の教育

知的財産権と商標権を守るためには、社内体制の整備と従業員の教育が不可欠です。
特許庁の資料によれば、知的財産権に関する社内の理解不足や管理体制の不備が、侵害事例の背景にあると指摘されています。(※)
知的財産権を守るための社内体制は、以下の3ステップで整備できます。
1.知的責任者の任命と権限付与
2.知財チェックプロセスの標準化
3.知財管理システムの導入
また、以下のポイントをおさえて従業員の教育プログラムを実施しましょう。
| 対象者 | 教育内容 |
| 全従業員 |
|
| 新入社員 |
|
| 開発・マーケティング部門 |
|
| 経営層・管理職 |
|
教育内容には、自社や他社の商標権の侵害事例を取り入れ、リアリティを持たせるのが効果的です。
また、e-ランニングと対面研修を組み合わせれば、効率的かつ効果的な教育が可能になります。
知的財産権を侵害されたら専門的な調査サービスを活用しよう
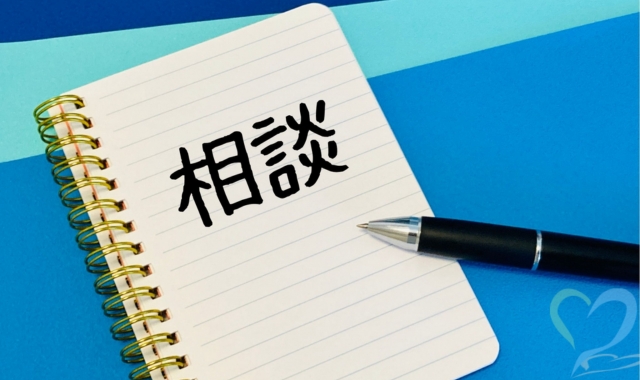
商標権をはじめとする知的財産権の侵害に直面した場合は、専門的な調査サービスを活用するのがおすすめです。
なぜなら、知的財産権侵害の立証には確実な証拠が必要だからです。
自社内での調査や証拠収集には、限界があるでしょう。
ファミリー調査事務所は、知的財産権侵害に関する証拠収集の専門知識と経験が豊富であるため、法的措置に有効な証拠を効率的かつ確実に収集します。
市場調査・インターネット上の侵害調査・実店舗での潜入調査など、一般企業では難しい高度な調査手法で証拠を収集します。
また、一般社団法人日本調査業協会加盟の信頼性と、WAD(世界探偵協会)の国際的なネットワークを生かした海外での知的財産権侵害調査も可能です。
知的財産権の侵害にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。24時間、365日お受けしています。